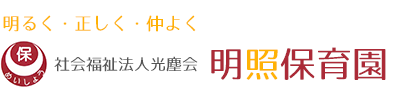カテゴリー
手作りコスメ講座
2019/10/30
手作りワークショップ種々と木々の岩城利英子氏をお招きしてのコスメ講座。
手作りコスメのメリットは、超リッチな成分を配合した潤いエッセンスを低コストで自分好みに作ることが出来ること。例えば今話題のヒアルロン酸、プロテオグリカン、米セラミドetc、女子が嬉しくなるフレーズを盛りだくさん配合しても市販の値段よりお安くなるから更に嬉しさ倍増(^o^)!。お肌もお財布もリッチになりますね☆
コスメ製作をしながら聞く、岩城先生の知って得するお肌とコスメのお話もお肌に潤いとツヤを与えてくれるような、そんな幸せ時間を過ごすことが出来き、より深く話を伺いたくなる雰囲気に質問も数多く、続々と美の求道者が誕生していました(*^_^*)
興味がある方は「種々と木々」で検索!
手作りコスメのメリットは、超リッチな成分を配合した潤いエッセンスを低コストで自分好みに作ることが出来ること。例えば今話題のヒアルロン酸、プロテオグリカン、米セラミドetc、女子が嬉しくなるフレーズを盛りだくさん配合しても市販の値段よりお安くなるから更に嬉しさ倍増(^o^)!。お肌もお財布もリッチになりますね☆
コスメ製作をしながら聞く、岩城先生の知って得するお肌とコスメのお話もお肌に潤いとツヤを与えてくれるような、そんな幸せ時間を過ごすことが出来き、より深く話を伺いたくなる雰囲気に質問も数多く、続々と美の求道者が誕生していました(*^_^*)
興味がある方は「種々と木々」で検索!
暑さも少しずつ和らぎ…
2019/09/18
戸外活動もしやすくなり、この日は園庭にみんなで出ました。
最初はそれぞれ好きな遊具で遊んでいたのですが、いつの間にか「だるまさんがころんだ」を始めたお友達にどんどん「いれて!」と声が掛かります。
そして後半は先生達も入れてぶどうさんからりんごさんまで、みんなで「はないちもんめ」をすることになりました。園児同士ジャンケンしたり、先生とジャンケンしたりと大盛り上がり!非常に楽しいひとときとなりました。
一昨年前に町の保育研究会で「伝承あそび」に関する研究を行いましたが、そこから意識的に取り入れている当園。伝承あそびは「だるまさんがころんだ」のような静と動を意識した動きで体幹やバランス感覚を養ったり、「はないちもんめ」のように異年齢間でも理解できる簡単なテーマを話し合う機会が設けられていたりと、子どもたちは知らず知らずのうちに多くの経験を積むことが出来ます。永く伝わる遊びには、それなりの理由があるのですね。
そんな盛り上がった様子を写真に収めておけば良かったのですが、盛り上がりすぎて撮るのを忘れていました(笑)
ということで、今回は自由遊びの後に行った運動会の練習の風景を…この日は玉入れとその玉のお片付け競争をしました♪
最初はそれぞれ好きな遊具で遊んでいたのですが、いつの間にか「だるまさんがころんだ」を始めたお友達にどんどん「いれて!」と声が掛かります。
そして後半は先生達も入れてぶどうさんからりんごさんまで、みんなで「はないちもんめ」をすることになりました。園児同士ジャンケンしたり、先生とジャンケンしたりと大盛り上がり!非常に楽しいひとときとなりました。
一昨年前に町の保育研究会で「伝承あそび」に関する研究を行いましたが、そこから意識的に取り入れている当園。伝承あそびは「だるまさんがころんだ」のような静と動を意識した動きで体幹やバランス感覚を養ったり、「はないちもんめ」のように異年齢間でも理解できる簡単なテーマを話し合う機会が設けられていたりと、子どもたちは知らず知らずのうちに多くの経験を積むことが出来ます。永く伝わる遊びには、それなりの理由があるのですね。
そんな盛り上がった様子を写真に収めておけば良かったのですが、盛り上がりすぎて撮るのを忘れていました(笑)
ということで、今回は自由遊びの後に行った運動会の練習の風景を…この日は玉入れとその玉のお片付け競争をしました♪
ハーブティー講座
2019/09/06
ハーブ農家が教える親子にオススメハーブ講座を、今年も赤石英二氏を講師にお招きして行われました。
昨年は、ママ達の「先生イケメン…♡」のつぶやきから始まったこの講座。エキゾチックな顔立ちの先生はいったいどこの出身なのかが気になっていたママ達。今年は「先生のご出身は沖縄ですか?」の囲み取材からのスタート(笑)
もちろん今年のハーブ講座もとっても興味深く、ハーブの種類や効能、妊産婦に良いハーブティーなど、見とれる暇のないくらい濃い内容。特にアップルミントは育てやすいハーブの一つらしく、ママ達にうれしい効能もたくさん!是非育ててみては。
試飲したハーブティーも美味しく、今年も癒されっぱなしのひとときでした♪
昨年は、ママ達の「先生イケメン…♡」のつぶやきから始まったこの講座。エキゾチックな顔立ちの先生はいったいどこの出身なのかが気になっていたママ達。今年は「先生のご出身は沖縄ですか?」の囲み取材からのスタート(笑)
もちろん今年のハーブ講座もとっても興味深く、ハーブの種類や効能、妊産婦に良いハーブティーなど、見とれる暇のないくらい濃い内容。特にアップルミントは育てやすいハーブの一つらしく、ママ達にうれしい効能もたくさん!是非育ててみては。
試飲したハーブティーも美味しく、今年も癒されっぱなしのひとときでした♪
ブルーベリー狩り
2019/09/06
今回のお出かけ支援では、七戸にある諏訪牧場でブルーベリー狩り体験をしてきました。
現地ではオーナーの方が快くお出迎えして下さって、同じ七戸ということもあり、お話が盛り上がりました。その中で、オーナーの子ども達が当園に通っていたという話が!私たちも嬉しくなって、誠に勝手ながら更に親近感を抱いた次第です♪
この日はとても暑い日でしたが、ブルーベリーツアーに参加させてもらっているかのように、諏訪牧場の奥様が親切にガイドして下さり、様々な品種を収穫するだけでなく、ブルーベリーのことも少し詳しくなることが出来ました!
収穫したブルーベリーはテントの中で心地いい風と共に美味しくいただきました。今回は、大人に負けじと止まらず食べていたのが子ども達!見ているだけで幸せな気持ちに(*^_^*)
ブルーベリーは、海外でおいて栄養価の高い食品である「スーパーフード」に定義されています。最高のロケーションで食したブルーベリーは、きっとママと子どもたちの健やかな日々を約束してくれることでしょう。
現地ではオーナーの方が快くお出迎えして下さって、同じ七戸ということもあり、お話が盛り上がりました。その中で、オーナーの子ども達が当園に通っていたという話が!私たちも嬉しくなって、誠に勝手ながら更に親近感を抱いた次第です♪
この日はとても暑い日でしたが、ブルーベリーツアーに参加させてもらっているかのように、諏訪牧場の奥様が親切にガイドして下さり、様々な品種を収穫するだけでなく、ブルーベリーのことも少し詳しくなることが出来ました!
収穫したブルーベリーはテントの中で心地いい風と共に美味しくいただきました。今回は、大人に負けじと止まらず食べていたのが子ども達!見ているだけで幸せな気持ちに(*^_^*)
ブルーベリーは、海外でおいて栄養価の高い食品である「スーパーフード」に定義されています。最高のロケーションで食したブルーベリーは、きっとママと子どもたちの健やかな日々を約束してくれることでしょう。
映える→調和する
2019/08/31
先日、J-CASTニュースというネットニュースサイトに「インスタ映え?撮影→8割食べ残しの非常識客 被害のジビエ料理店は『出禁』をきめた」という記事が載っていました。「写真撮影やネットへの投稿自体は全く問題はないのだが、写真のためだけに注文をして、ほとんど手をつけずに残すのは非常に悲しい。お金を払ったらインスタ映えの為に料理を大量に残しても構わないと思っている方々はご遠慮下さい。命をもらってその肉で生計を立てる者として、こんなに悲しいことはありません。」とネットに投稿した店主の想いが記事となっていました。それに対し、様々な意見が寄せられたようですが、その中でこのような反応があったそうです。「張り紙で、残すの禁止と書いていない以上、その人達の行動に問題はないと思います。ただ考え方はとても大好きです。」私は、前半部分の内容に少し考えるところがありました。マナーもルールも根底は、みんなが気持ちよく生活することを目的としているはずです。そして、マナーの曖昧な部分や基本的な部分を明確にし、より解りやすく守るために設けられたものがルールなのではと思います。そう考えると、マナーを無視すること自体「行動に問題がない」とは言えないのではないかと感じます。
9月の徳目は「報恩感謝(ほうおんかんしゃ)」「あらゆることをありがたく感じよう」ということです。上記の件は、頂く命、そして料理が出来るまでに関わった方への感謝、つまり「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を身にしみて感じていれば起こらなかったことではないでしょうか。マナーとは周りへの気配り、つまり周囲と繋がっていられる、支えられている事への感謝を行動に表したものだと私は考えます。改めて、謙虚でいる事の重要さを考えさせられるニュースでした。
せっかくの「インスタ映え」が「インスタ蠅」と揶揄されないように気を付けたいものです。と、今回の画像に使うために、インスタ映えしそうなジビエ料理を一生懸命ネット検索しました…(2019.9)
9月の徳目は「報恩感謝(ほうおんかんしゃ)」「あらゆることをありがたく感じよう」ということです。上記の件は、頂く命、そして料理が出来るまでに関わった方への感謝、つまり「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を身にしみて感じていれば起こらなかったことではないでしょうか。マナーとは周りへの気配り、つまり周囲と繋がっていられる、支えられている事への感謝を行動に表したものだと私は考えます。改めて、謙虚でいる事の重要さを考えさせられるニュースでした。
せっかくの「インスタ映え」が「インスタ蠅」と揶揄されないように気を付けたいものです。と、今回の画像に使うために、インスタ映えしそうなジビエ料理を一生懸命ネット検索しました…(2019.9)
芸術体験
2019/08/29
今回の新谷祥子さんによる芸術体験では、新谷さんご自身が翻訳されたオノマトペの絵本「こわす」「たてる」に、職員の読み聞かせに合わせて、新谷さんが様々な「音」を添えて下さいました。いつもと雰囲気の違う読み聞かせに、子どもたちは真剣なまなざしで絵本の世界へ。何度も読んだ絵本でも、音を入れることで更に広がりが生まれることを実感しました。
他にも、新谷さんが歌に合わせふわふわの布を舞上げると、そこからも柔らかな音が聞こえてきそうな感覚に(*^_^*)
最後には様々な楽器の音を体験。中には動物の爪で作った民族楽器もあるとか!子どもたちは興味津々で音を奏でていました♪
他にも、新谷さんが歌に合わせふわふわの布を舞上げると、そこからも柔らかな音が聞こえてきそうな感覚に(*^_^*)
最後には様々な楽器の音を体験。中には動物の爪で作った民族楽器もあるとか!子どもたちは興味津々で音を奏でていました♪
ホームカミングデー
2019/08/26
昨年はずっと仮園舎で生活していたので、去年の年長さんを新しい保育園に招待しました♪
完成して一度は中を見学した事はありましたが、1日生活するのは今回が初めて。みんなワクワクしながら登園してきました。また、昨年実習にきた先生が、丁度2度目の実習期間だったため、1年生達は大喜び!
1年生になったみんなは、更に頼もしいお兄さんお姉さんになっていて、園のみんなと楽しく遊びながらもお世話をしている様子が見られます。
この日は暑かったため、中庭で水遊び。意外と広い中庭でみんな思いっきり楽しみました。
1年生にとっても、園児にとっても思い出深い1日となったことでしょう。
完成して一度は中を見学した事はありましたが、1日生活するのは今回が初めて。みんなワクワクしながら登園してきました。また、昨年実習にきた先生が、丁度2度目の実習期間だったため、1年生達は大喜び!
1年生になったみんなは、更に頼もしいお兄さんお姉さんになっていて、園のみんなと楽しく遊びながらもお世話をしている様子が見られます。
この日は暑かったため、中庭で水遊び。意外と広い中庭でみんな思いっきり楽しみました。
1年生にとっても、園児にとっても思い出深い1日となったことでしょう。
仲良く
2019/08/23
「『よろこんであたえる人間となろう』─ものがあればものを ちからがあればちからを ちしきがあればちしきを みんなにあたえよう なければ自分のなかに そだてて あたえよう 花は美しさをおしまず 小鳥は たのしい歌をおしまない だれにでもあたえている あたえるとき 人は ゆたかになりおしむとき いのちは まずしくなる よろこんで あたえる人間となろう─」
これは浄土宗に制定されている「六つのねがい」のひとつです。この中で私が目を惹かれたのは、「なければ 自分のなかにそだてて あたえよう」「あたえるとき 人は ゆたかになる」という箇所です。難しいことではありますが、心に留めておきたいものです。
8月の徳目は「自利利他(じりりた)」「自分を高め人に尽くそう」です。上記の文章はまさに自利利他を表しているように感じます。自分を高めることは自分の為、つまり「自利」です。一方で、その高めたものを周りに振り向けることは「利他」ではありますが、それは自分の心を豊かにし、与えたものは回り回って必ず自分へ還ってくる「自利」にもなります。明照の保育目標「仲良く」にはそのような自利利他の想いも込められていると思います。今の世の中は個を大切にすることが重要になっており、もちろんとても大事なことです。但し、根底に「自分たちは周りに生かされている」という謙虚な想いがなければ、「個の尊重」は「自分さえ良ければ良い」にすり替わってしまいかねません。子どもたちの自主性を育てながら、それぞれが培った力を周りに振り分ける協調性も大事に取り組んでまいります。
この話はどうぞ自分だけに留めず、「テープを回して」でも他の方にもお伝え下さい。(2019.8)
これは浄土宗に制定されている「六つのねがい」のひとつです。この中で私が目を惹かれたのは、「なければ 自分のなかにそだてて あたえよう」「あたえるとき 人は ゆたかになる」という箇所です。難しいことではありますが、心に留めておきたいものです。
8月の徳目は「自利利他(じりりた)」「自分を高め人に尽くそう」です。上記の文章はまさに自利利他を表しているように感じます。自分を高めることは自分の為、つまり「自利」です。一方で、その高めたものを周りに振り向けることは「利他」ではありますが、それは自分の心を豊かにし、与えたものは回り回って必ず自分へ還ってくる「自利」にもなります。明照の保育目標「仲良く」にはそのような自利利他の想いも込められていると思います。今の世の中は個を大切にすることが重要になっており、もちろんとても大事なことです。但し、根底に「自分たちは周りに生かされている」という謙虚な想いがなければ、「個の尊重」は「自分さえ良ければ良い」にすり替わってしまいかねません。子どもたちの自主性を育てながら、それぞれが培った力を周りに振り分ける協調性も大事に取り組んでまいります。
この話はどうぞ自分だけに留めず、「テープを回して」でも他の方にもお伝え下さい。(2019.8)
攻める親切
2019/08/23
「障害者の側に立って、味方になってくれている人たち、要するに家族や福祉や介護関係、ボランティアの人たちなどが、障害者に理解のない人たちから我々を守ろう、少しでも社会に参加させようと過剰に振る舞い、結果的に社会と我々とを隔絶させてしまっているのをまま目にする」ホーキング青山という肢体不自由のお笑い芸人さんの言葉です。この言葉を聞いたときにハッとさせられました。「過剰」な想いが時としてマイナスに働いてしまうこともあります。そしてそれは、子育てでも同じようなことが言えるのではないかと考えさせられました。
「除菌」「抗菌」という言葉を様々な場面で耳にすることが多くなり、周りで子どもたちを菌から守る意識がここ数年非常に高まっていると感じます。ある一定は必要なことでありますが、子どもたち自身の免疫力を高める手立ても同時に考えていかなくてはなりません。また、子どもたちが誰でも安全で安心して遊べる環境を整えるため、屋外遊具がシンプルで遊びやすいものへと変わりつつあります。もちろん、そのような視点も大事なことであります。しかし、自分は今どのくらいのことができ、どこまでが安全で、どこからが危険なのか、子どもたち各々が判断する力もまた必要なことだと考えます。守ろうとする善意や、誰もが同じようにという配慮は、度を過ぎると、子どもたちの成長の妨げになってしまうものかもしれません。
「今月の徳目は「布施奉仕(ふせほうし)」「誰にでも親切にしよう」ということです。世間一般的に弱い立場とされる人へは手を差し伸べ、守ることを考えがちですが、相手の為になるかどうかが親切には重要であり、場合によっては「守らない」ことが親切になることもあるのだと思います。
題名がイマイチ解りづらいですが、触れないこともまた親切です。(2019.7)
「除菌」「抗菌」という言葉を様々な場面で耳にすることが多くなり、周りで子どもたちを菌から守る意識がここ数年非常に高まっていると感じます。ある一定は必要なことでありますが、子どもたち自身の免疫力を高める手立ても同時に考えていかなくてはなりません。また、子どもたちが誰でも安全で安心して遊べる環境を整えるため、屋外遊具がシンプルで遊びやすいものへと変わりつつあります。もちろん、そのような視点も大事なことであります。しかし、自分は今どのくらいのことができ、どこまでが安全で、どこからが危険なのか、子どもたち各々が判断する力もまた必要なことだと考えます。守ろうとする善意や、誰もが同じようにという配慮は、度を過ぎると、子どもたちの成長の妨げになってしまうものかもしれません。
「今月の徳目は「布施奉仕(ふせほうし)」「誰にでも親切にしよう」ということです。世間一般的に弱い立場とされる人へは手を差し伸べ、守ることを考えがちですが、相手の為になるかどうかが親切には重要であり、場合によっては「守らない」ことが親切になることもあるのだと思います。
題名がイマイチ解りづらいですが、触れないこともまた親切です。(2019.7)
新たな気づき
2019/08/22
新園舎に引っ越しをしてもうすぐ1ヶ月。新しい場所ならではの子どもたちに関する発見がこの期間でいくつかありました。その中で、特に印象深かったものを紹介します。
それは新園舎への登園初日のこと。プレイルームを見渡し「うわぁ」と子どもたちが歓声を上げる中、「ののさまはどこにいるの?」との声が聞こえてきました。その声を聞いたとき、非常に嬉しい気持ちになりました。
神仏や自然に対してよく使われる言葉に「畏敬の念」というものがあります。畏れ(おそれ)敬う心情のことで、「畏れる」とはつつしみをもって相対する心情を表します。人は一人では生きられません。「畏敬の念」を抱くことで自分が様々なお陰で生かされることを感じ、謙虚な気持ちになれます。「ののさまはどこにいるの?」は直接「畏敬の念」につながるわけではありませんが、子どもたちの心に紛れもなく「ののさま」が存在し、気にかけている、そんな思いが私を嬉しい気持ちにさせたのだと思います。仏教保育ならではの感覚を育てられていることにありがたい思いになりました。
6月の徳目は「生命尊重(せいめいそんちょう)」「命を大切にしよう」です。「私と小鳥と鈴と」で有名な童謡詩人である金子みすゞの詩に「星とたんぽぽ」というものがあります。その中で「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」という一節があり、見えないものや見えにくいものの大切さを伝えています。目に見えないものにも思いを馳せ、生かされていることを感じることもまた、命を大切にすることにつながっていくのだと思います。実際には目に見えない「ののさま」に対する子どもたちの思いを、これからも大事にしていきたいものです。
新園舎に引っ越しして1ヶ月。子どもたちの様々な育ちを発見する一方で、引っ越しの際に大事にしまった書類を未だ発見できずにいます…(2019.6)
それは新園舎への登園初日のこと。プレイルームを見渡し「うわぁ」と子どもたちが歓声を上げる中、「ののさまはどこにいるの?」との声が聞こえてきました。その声を聞いたとき、非常に嬉しい気持ちになりました。
神仏や自然に対してよく使われる言葉に「畏敬の念」というものがあります。畏れ(おそれ)敬う心情のことで、「畏れる」とはつつしみをもって相対する心情を表します。人は一人では生きられません。「畏敬の念」を抱くことで自分が様々なお陰で生かされることを感じ、謙虚な気持ちになれます。「ののさまはどこにいるの?」は直接「畏敬の念」につながるわけではありませんが、子どもたちの心に紛れもなく「ののさま」が存在し、気にかけている、そんな思いが私を嬉しい気持ちにさせたのだと思います。仏教保育ならではの感覚を育てられていることにありがたい思いになりました。
6月の徳目は「生命尊重(せいめいそんちょう)」「命を大切にしよう」です。「私と小鳥と鈴と」で有名な童謡詩人である金子みすゞの詩に「星とたんぽぽ」というものがあります。その中で「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」という一節があり、見えないものや見えにくいものの大切さを伝えています。目に見えないものにも思いを馳せ、生かされていることを感じることもまた、命を大切にすることにつながっていくのだと思います。実際には目に見えない「ののさま」に対する子どもたちの思いを、これからも大事にしていきたいものです。
新園舎に引っ越しして1ヶ月。子どもたちの様々な育ちを発見する一方で、引っ越しの際に大事にしまった書類を未だ発見できずにいます…(2019.6)
破るために守る
2019/08/22
【適切にルールを破る方法を見つけるために、ルールを学びなさい】チベット仏教の偉いお坊さんであるダライ・ラマ14世の言葉です。「ルールを破りなさい」という言葉に違和感を覚える人もいるかもしれません。しかし、「適切に」が非常に深い意味を持っているように感じます。日本には「守破離(しゅはり)」という言葉があります。これは、武道や茶道などの修業に際して、まず型を「守り」、しっかりに身につけた者は、他流派なども含め自分に合った型を研究して元の型を「破り」、そしてさらに鍛錬を重ね、自分独自の型を作って元の型から「離れ」ていく、という考え方です。ダライラマの言う「適切に破る」とは、より良いものを生み出すという意味で、そのためには元々のルールにどんな意味や目的があるかを理解する必要があるということだと思います。実際に体験することで気づくこともあるはずです。まずはルールを守ることが大切なのではないでしょうか。
今月の徳目は「持戒和合(じかいわごう)」です。「きまりを守り、集団生活を楽しもう」という意味です。今はルールを覚える時期であると思います。仏教で大切なルールとは「みんなとともにより良く生きる」であり「共生(ともいき)」と言います。社会の中で生きている私たちは何をしても許されるわけではありません。規則や枠があり、その中で考えるからこそ工夫や創造が生まれ、それが楽しみとなっていきます。一定のルールがある集団生活の中で、自主性と自分勝手の違いを私たち大人はしっかりと見極め伝えていかなくてはならないと感じています。
平日はお酒を飲まないようにするマイルールが、たまにはOKになり、夜お米を食べないマイルールが、ちょくちょく食べるようになりと、より良い(?)ルールへと変貌を遂げています。(2019.5)
今月の徳目は「持戒和合(じかいわごう)」です。「きまりを守り、集団生活を楽しもう」という意味です。今はルールを覚える時期であると思います。仏教で大切なルールとは「みんなとともにより良く生きる」であり「共生(ともいき)」と言います。社会の中で生きている私たちは何をしても許されるわけではありません。規則や枠があり、その中で考えるからこそ工夫や創造が生まれ、それが楽しみとなっていきます。一定のルールがある集団生活の中で、自主性と自分勝手の違いを私たち大人はしっかりと見極め伝えていかなくてはならないと感じています。
平日はお酒を飲まないようにするマイルールが、たまにはOKになり、夜お米を食べないマイルールが、ちょくちょく食べるようになりと、より良い(?)ルールへと変貌を遂げています。(2019.5)
お耳澄ますと
2019/08/19
昔、ネパールの山登りツアーに参加した時のことです。山登りといっても、イモトアヤコさんのような、壮絶な登山ではなく、ハイキングのような比較的穏やかな山登りです。その山登りでは2日ほど山でキャンプをしたのですが、夜空に圧倒されました。周りに光がほとんどない状態での空はまさに満天の星。人工衛星の光も見えるほどで、流れ星も数分に1度は見られます。また、周りに音のするものがない静寂の世界。「こんなに静かだと流れ星の音が聞こえてきそうですよね。」ツアーに参加している他のお客さんが言うように、耳を澄ますと本当に流れ星の音が聞こえてくるのではと思うほどでした。耳を澄ませば澄ますほど、心が穏やかになっていくような気がしたのを今でも思い出します。
今月の徳目(より良く生きるための基本となるもの)は「合掌(がつしよう)聞法(もんぽう)」「敬う心をもって人の話を聞こう」という意味です。人と向き合うときはもちろんですが、物事と向き合うときにも必要な姿勢ではないでしょうか。耳を傾けようとすることで一度立ち止まることができ、一度立ち止まることで心に余裕が生まれ、ひたむきな態度になれるのだと思います。音に溢れた現代社会において、完全に音のない生活を送ることは難しく、「耳を澄ます」ことをする機会があまり多くありません。だからこそ、耳を澄ます機会を作り、物事とゆっくりと向き合うことで、聞こえたり見えたりするものがあるのかもしれません。
この文章を作りながら、私自身も耳を澄まそうと試みてみるのですが、最近メディアに登場してきたお笑い芸人の「パンケーキ食べたい」が、何故か頭の中でリピートしてしまう、テレビにまみれた生活をしている私です。(2019.4)
今月の徳目(より良く生きるための基本となるもの)は「合掌(がつしよう)聞法(もんぽう)」「敬う心をもって人の話を聞こう」という意味です。人と向き合うときはもちろんですが、物事と向き合うときにも必要な姿勢ではないでしょうか。耳を傾けようとすることで一度立ち止まることができ、一度立ち止まることで心に余裕が生まれ、ひたむきな態度になれるのだと思います。音に溢れた現代社会において、完全に音のない生活を送ることは難しく、「耳を澄ます」ことをする機会があまり多くありません。だからこそ、耳を澄ます機会を作り、物事とゆっくりと向き合うことで、聞こえたり見えたりするものがあるのかもしれません。
この文章を作りながら、私自身も耳を澄まそうと試みてみるのですが、最近メディアに登場してきたお笑い芸人の「パンケーキ食べたい」が、何故か頭の中でリピートしてしまう、テレビにまみれた生活をしている私です。(2019.4)
見
2019/08/19
お寺の庫裏の屋根から落ちる雪は毎年2m以上の高さまで達し、幅広く積ります。息子たちは「かまくらが作れそうだね」と見るたびに話していたので、先日の休日に重い腰を上げかまくら作りをすることにしました。最初は張り切っていた子どもたち。しかし雪をかきだしてもかきだしても一向に広がらない穴に、次第にげんなり。とうとう次男と長女は掘っている横で尻滑りを始める始末。長男と私でコツコツと掘り進めることになりました。しばらくすると、ようやく1人が入れそうな広さに。すると、「面白くなってきた」と俄然やる気が出てきた長男は黙々と掘り進めました。一方次男たちは、何度も尻滑りしているうちに程よいコースができたため、コースのスタートまで上りやすくするための階段を作り始めました。実際上ってみては高さを調節したり、幅を考えるなど試行錯誤を繰り返していました。そこからはあっという間の2時間。かなり立派な、家族全員入れるかまくらと、階段付きの尻滑りゲレンデができました。
さて、3月の徳目は「智慧希望(ちえきぼう)」「希望をもち、楽しく暮らそう」という意味です。何事も初めてのものは見通しが持てるまでには時間がかかります。しかし、見通しが持てると「希望」が生まれ、希望が生まれると困難にも立ち向かえるようになり、いずれはその困難すら「楽しく」なるのだと思います。子どもが初めてのものに立ち向かう時、見通しが持てるよう配慮することが私たち大人の役目なのではないでしょうか。進級進学を迎え、新たなステージに立つ子どもたちが見通しを持てるようしっかりサポートしていきたいものです。
子どもたちの作ったかまくらとゲレンデの大作を写真に撮っておけばよかったと、この文章を書きながら非常に後悔している見通しの甘い私です。(2019.3)
さて、3月の徳目は「智慧希望(ちえきぼう)」「希望をもち、楽しく暮らそう」という意味です。何事も初めてのものは見通しが持てるまでには時間がかかります。しかし、見通しが持てると「希望」が生まれ、希望が生まれると困難にも立ち向かえるようになり、いずれはその困難すら「楽しく」なるのだと思います。子どもが初めてのものに立ち向かう時、見通しが持てるよう配慮することが私たち大人の役目なのではないでしょうか。進級進学を迎え、新たなステージに立つ子どもたちが見通しを持てるようしっかりサポートしていきたいものです。
子どもたちの作ったかまくらとゲレンデの大作を写真に撮っておけばよかったと、この文章を書きながら非常に後悔している見通しの甘い私です。(2019.3)
願
2019/08/10
「節分の夜に、恵方に向かって願い事を思い浮かべながら丸かじり(丸かぶり)し、言葉を発せずに最後まで一気に食べきると願い事がかなう」とされる恵方巻。大阪発祥の風習と言われているようですが、起源には諸説あり、実際のところは不明な点が多く定説は存在しないそうです。ちなみに今年の恵方は東北東、細かくいうと東北東やや東とのことです。全国的にはここ10年ぐらいのうちに節分の風物詩として定着してきました。
そんな恵方巻の「願い事を思い浮かべながら」「言葉を発せず」という部分から、とあるプロのスポーツ選手のインタビューを思い出しました。「私は、試合のイメージはもちろん、勝った瞬間の喜ぶ自分の姿や表彰式の様子までイメージして大会に臨んでいます。」といった内容です。実際に、未来の自分を具体的にイメージする、特にそのイメージが鮮明なカラーに描けるまで高めるとその姿に近づくことが出来る、という話はよく聞きます。忙しいときや大変なときこそ一度立ち止まり、自分の考えをじっくり整理する、そんな時間をもとうとする心の余裕が欲しいものですね。
さて、2月の徳目は「禅定静寂(ぜんじょうせいじゃく)」、「よく考え、落ち着いた暮らしをしよう」です。近年は、大量の売れ残りを「捨ててしまう」問題がクローズアップされ、ネガティブな話題としても取り上げられている恵方巻。それでも、節分の日には鬼に投げた豆や恵方巻を食べながら、どんなお願い事をしたのかや今年はどんな1年にしたいのかなど、家族でゆっくりイメージを高め合う時間が作られれば、恵方巻の風習は「捨てたもの」ではないですね。(2019.2)
そんな恵方巻の「願い事を思い浮かべながら」「言葉を発せず」という部分から、とあるプロのスポーツ選手のインタビューを思い出しました。「私は、試合のイメージはもちろん、勝った瞬間の喜ぶ自分の姿や表彰式の様子までイメージして大会に臨んでいます。」といった内容です。実際に、未来の自分を具体的にイメージする、特にそのイメージが鮮明なカラーに描けるまで高めるとその姿に近づくことが出来る、という話はよく聞きます。忙しいときや大変なときこそ一度立ち止まり、自分の考えをじっくり整理する、そんな時間をもとうとする心の余裕が欲しいものですね。
さて、2月の徳目は「禅定静寂(ぜんじょうせいじゃく)」、「よく考え、落ち着いた暮らしをしよう」です。近年は、大量の売れ残りを「捨ててしまう」問題がクローズアップされ、ネガティブな話題としても取り上げられている恵方巻。それでも、節分の日には鬼に投げた豆や恵方巻を食べながら、どんなお願い事をしたのかや今年はどんな1年にしたいのかなど、家族でゆっくりイメージを高め合う時間が作られれば、恵方巻の風習は「捨てたもの」ではないですね。(2019.2)
零
2019/08/10
お笑いコンビサンドウィッチマンの伊達みきおさんによる「ゼロカロリー理論」。「カステラは潰すととっても小さくなるからゼロカロリー。」から始まり「ドーナツは真ん中が空いているし、形で0を表しているからゼロカロリー。」「カロリーは熱に弱いから唐揚げはゼロカロリー。」など、現実的にはあり得ない話ではありますが、その視点に思わずクスッとしてしまいます。このゼロカロリー理論は話題を呼び、歌にもなるほど盛り上がりを見せました。この理論がこれだけ人気を集めているのは、視点の面白さだけではなく、どこかでそうであって欲しいと願ったり、健康を意識しすぎることに少し息苦しさを感じている部分もあるのではないかと考えます。
健康に気を付けることはとても大事なことですが、健康に気を使いすぎて何も楽しめず余裕がなくなり、心が不健康になってしまうのは本末転倒です。心も体も健康になるためには、我慢だけではなく、少し気を抜ける場面や失敗を笑い飛ばせるくらいの柔らかさが必要なのかもしれません。
さて、1月の徳目は「和顔愛語(わげんあいご)」、「柔らかい顔で、優しい言葉を」です。育児においてもこの精神は大切なのではと最近強く感じます。子どもの間違いを正すことは大事ですが、そこばかりに目がいってしまうと口調が厳しくなってしまい、その言葉を受ける側も萎縮してしまいます。時には余裕を持った対応が思いを伝わりやすくし、その結果、受ける側は気持ちを新たにでき、互いに柔らかい気持ちになるのではないでしょうか。
年末年始は飲食することが楽しみな行事が目白押しで、体重増加が気になるところです。しかし、たくさん飲み食いして柔らかい「まん丸」な顔になったその時、きっと「O」カロリーになるのだと思います(諸説あり)。(2019.1)
健康に気を付けることはとても大事なことですが、健康に気を使いすぎて何も楽しめず余裕がなくなり、心が不健康になってしまうのは本末転倒です。心も体も健康になるためには、我慢だけではなく、少し気を抜ける場面や失敗を笑い飛ばせるくらいの柔らかさが必要なのかもしれません。
さて、1月の徳目は「和顔愛語(わげんあいご)」、「柔らかい顔で、優しい言葉を」です。育児においてもこの精神は大切なのではと最近強く感じます。子どもの間違いを正すことは大事ですが、そこばかりに目がいってしまうと口調が厳しくなってしまい、その言葉を受ける側も萎縮してしまいます。時には余裕を持った対応が思いを伝わりやすくし、その結果、受ける側は気持ちを新たにでき、互いに柔らかい気持ちになるのではないでしょうか。
年末年始は飲食することが楽しみな行事が目白押しで、体重増加が気になるところです。しかし、たくさん飲み食いして柔らかい「まん丸」な顔になったその時、きっと「O」カロリーになるのだと思います(諸説あり)。(2019.1)
進
2019/08/09
「子供の科学」という創刊以来90年以上経つ、子ども向けの月刊雑誌があります。小学生の頃、実験などの科学的分野が好きだった私はあまり本を読まない人間であったものの、その本はそこそこ読んでいた記憶があります。最近、私の母が孫にも読ませたいと購入を再開し、私も懐かしさから久々に手に取ってみました。
本の内容には、パソコンのプログラミング方法など当時の子ども向けには考えもしないような記事も増え、科学の進歩を感じさせます。その中で非常に興味深い実験記事がありました。それは、授業内容をノートに手書きして受けたグループとパソコンに打ち込んで受けたグループが、後にその授業に関するテストを受けると、手書きして受けたグループの方が成績が良いという結果が出たというものです。世の中は科学の力でどんどん便利になっていきますが、不便や苦労が人を成長させることもあります。一見科学の進歩を否定するように見えるこの記事を、科学雑誌があえて載せているということに考えさせられるものがありました。
12月の徳目は「忍辱持久(にんにくじきゅう)」、「根気強く取り組もう」です。「耐える」と考えると、どうしても苦しくて辛いイメージをもってしまいますが、「便利だから楽しいんじゃない。不便さの中にこそ幸せはある(所ジョージ)」のように、本当の面白さは大変の中にこそあると気づけると、「忍辱持久」はもっとポジティブな見方が出来るような気がします。
実を言うと私、高校に入ってから「mol(モル)」という化学単位の難しさにすぐ挫折して、理科から離れてしまったタイプです。当時パソコンが今くらい便利なら楽に理解できたのに…成長がありません。(2018.12)
本の内容には、パソコンのプログラミング方法など当時の子ども向けには考えもしないような記事も増え、科学の進歩を感じさせます。その中で非常に興味深い実験記事がありました。それは、授業内容をノートに手書きして受けたグループとパソコンに打ち込んで受けたグループが、後にその授業に関するテストを受けると、手書きして受けたグループの方が成績が良いという結果が出たというものです。世の中は科学の力でどんどん便利になっていきますが、不便や苦労が人を成長させることもあります。一見科学の進歩を否定するように見えるこの記事を、科学雑誌があえて載せているということに考えさせられるものがありました。
12月の徳目は「忍辱持久(にんにくじきゅう)」、「根気強く取り組もう」です。「耐える」と考えると、どうしても苦しくて辛いイメージをもってしまいますが、「便利だから楽しいんじゃない。不便さの中にこそ幸せはある(所ジョージ)」のように、本当の面白さは大変の中にこそあると気づけると、「忍辱持久」はもっとポジティブな見方が出来るような気がします。
実を言うと私、高校に入ってから「mol(モル)」という化学単位の難しさにすぐ挫折して、理科から離れてしまったタイプです。当時パソコンが今くらい便利なら楽に理解できたのに…成長がありません。(2018.12)
楽
2019/08/09
「最初から苦しむ方向をとったから後は楽になった。最初楽した者はその後苦しむ。」これは、HONDAの創業者、本田宗一郎氏の言葉です。ビジネスの本などによく掲載されており、成功するための鍵と言われています。実際に、最初の頃すぐにはうまくいかず試行錯誤を繰り返している企業ほど、後に長く成功するという調査結果もあるそうです。よくよく考えると確かにその通りで、最初に深く考えもしないで単純に成功しているところの真似をしたり、誰かに頼って努力をしないでいると、自分で考える力や習慣が身につきません。そして、後に何か苦労をしなくてはならないとき、楽から抜け出せず、努力の仕方も分からず、本来の苦労以上の苦労をしてしまうのだと思います。はじめの時期にどんな経験をし、どんな力を身につけ、それをその後どうするのか、そのことを念頭に置いてはじめのうちに努力することが後々の方向性に大きく関わってくるのだと思います。
さて、11月の徳目は「精進努力(しょうじんどりょく)」、「最後までやり遂げよう」です。子育ては長い道のりではありますが、「三つ子の魂百まで」ということわざがある通り、本田宗一郎氏の言葉は子育てにも当てはまることだと思います。この時期にしっかり子どもと向き合う努力が、私たち大人にとって子育ての大きな財産になり、何より子どもたちにとってその後のスムーズな成長に繋がるはずです。そして、園に預けているから、ご家庭に帰したからあとは関係ないではなく、様々な角度から互いに共通理解を図り協力し合いながら子育てしていくことこそが、子どもを更に成長させるものだと信じています。お陰様で、本園では、園と家庭の両輪で子育てが出来ていると強く感じます。これからも相互協力しながら、今後の子育てがより順調に進むよう、今この時期を大事にしていきたいと思います。
毎回おたよりの文章を書く際に、「きっと何かが降りてきてひらめくはず!」と、結局〆切ギリギリになってしまい、後で苦しむタイプの私です…(2018.11)
さて、11月の徳目は「精進努力(しょうじんどりょく)」、「最後までやり遂げよう」です。子育ては長い道のりではありますが、「三つ子の魂百まで」ということわざがある通り、本田宗一郎氏の言葉は子育てにも当てはまることだと思います。この時期にしっかり子どもと向き合う努力が、私たち大人にとって子育ての大きな財産になり、何より子どもたちにとってその後のスムーズな成長に繋がるはずです。そして、園に預けているから、ご家庭に帰したからあとは関係ないではなく、様々な角度から互いに共通理解を図り協力し合いながら子育てしていくことこそが、子どもを更に成長させるものだと信じています。お陰様で、本園では、園と家庭の両輪で子育てが出来ていると強く感じます。これからも相互協力しながら、今後の子育てがより順調に進むよう、今この時期を大事にしていきたいと思います。
毎回おたよりの文章を書く際に、「きっと何かが降りてきてひらめくはず!」と、結局〆切ギリギリになってしまい、後で苦しむタイプの私です…(2018.11)
信
2019/08/08
スペインに「人間の塔」という無形文化遺産があります。カタルーニャ地方で200年以上続く伝統的な行事であり、近年ではメンバーの身長や体重をデータ化し、それぞれ最適なポジション配置を組むところからこの行事は始まります。塔の頂点の子どもは、大人達が絶対に守ってくれると信じ、土台や中段の大人達は、自分たちを信じてくれる子どもたちを絶対に落とさない強い決意をもって、緻密な計算と互いを信じ合う人々の絆によって塔が形成されていく光景は圧巻であり、正に命をかけて皆が真剣に取り組む姿勢は、見る者に様々な想いをもたらします。
さて、10月の徳目は「同時協力(どうじきょうりょく)」、「お互いに助け合おう」ということです。近年日本では、子どもにとって少しでもリスクがあるとすぐに排除することが主流となっています。一方で、過度な排除により子どもたちの「運動能力」や「危険察知能力」が低下し、大きなケガや事故が増えている状況も生まれつつあります。子どもをケガから守ると言うよりも、大人が極力責任を負わないような流れにも見えます。私たち大人は、子どもがケガをしないように何もさせないのではなく、子どもの主体的な活動を通じて、万が一失敗しても最小限のケガで大きな価値が生まれるよう、安全対策のバランスをとることが大事です。「人間の塔」は極端な例ではありますが、リスクに向き合うことも時には容認し、私たち大人が協力し合って見守ることも大切なのではないでしょうか。
「人間の塔」で、普段どんなテレビ番組を見ているか、気づかれたかも知れません。ついでに同番組で有名なキラキラの話もしようかと思いましたが、様々なリスクを考慮し向き合えませんでした。(2018.10)
さて、10月の徳目は「同時協力(どうじきょうりょく)」、「お互いに助け合おう」ということです。近年日本では、子どもにとって少しでもリスクがあるとすぐに排除することが主流となっています。一方で、過度な排除により子どもたちの「運動能力」や「危険察知能力」が低下し、大きなケガや事故が増えている状況も生まれつつあります。子どもをケガから守ると言うよりも、大人が極力責任を負わないような流れにも見えます。私たち大人は、子どもがケガをしないように何もさせないのではなく、子どもの主体的な活動を通じて、万が一失敗しても最小限のケガで大きな価値が生まれるよう、安全対策のバランスをとることが大事です。「人間の塔」は極端な例ではありますが、リスクに向き合うことも時には容認し、私たち大人が協力し合って見守ることも大切なのではないでしょうか。
「人間の塔」で、普段どんなテレビ番組を見ているか、気づかれたかも知れません。ついでに同番組で有名なキラキラの話もしようかと思いましたが、様々なリスクを考慮し向き合えませんでした。(2018.10)
お泊まり保育③
2019/08/07
夜のお楽しみは、二人羽織と福笑いを融合させたオリジナルゲーム。座っている先生の後にりんごさん達。
そして本当は花火をする予定だったけれど、園庭が雨で濡れていたので、屋根のある場所から噴火花火を楽しみました。
今回はほぼ全員が親やおじいちゃんおばあちゃん以外とお泊まりするのが初めてだった様ですが、ホームシックになる事もなくすんなり就寝。思い思いの寝相でグッスリ休みました(笑)
次の日はみんな元気に起床!プレイルームでラジオ体操をしてから、外に散歩へ出かけました。天気も良くなり、気持ちの良い朝。お寺の敷地内をぐるっと回り、保育園に戻ってきてから朝食。朝もみんなモリモリ食べました。
その後帰り支度をするとお家の方が続々お迎えに。もしかしたら一番寂しかったのはお家の人たちかも知れませんね♪
そして本当は花火をする予定だったけれど、園庭が雨で濡れていたので、屋根のある場所から噴火花火を楽しみました。
今回はほぼ全員が親やおじいちゃんおばあちゃん以外とお泊まりするのが初めてだった様ですが、ホームシックになる事もなくすんなり就寝。思い思いの寝相でグッスリ休みました(笑)
次の日はみんな元気に起床!プレイルームでラジオ体操をしてから、外に散歩へ出かけました。天気も良くなり、気持ちの良い朝。お寺の敷地内をぐるっと回り、保育園に戻ってきてから朝食。朝もみんなモリモリ食べました。
その後帰り支度をするとお家の方が続々お迎えに。もしかしたら一番寂しかったのはお家の人たちかも知れませんね♪
お泊まり保育②
2019/08/07
プールの後は買い出しした材料を下ごしらえ。包丁を上手に使いながら野菜を切りました。夜が楽しみです。
夕方には温泉へ。大きな浴槽に最初は戸惑う子もいましたが、最終的には「まだ入っていたい!」(笑)みんなで入るお風呂は楽しいね!
そして夕食。ビュッフェ形式でサラダやカレーなどを自分が食べたい分だけ盛りつけ。自分たちで育てたり作ったりした事もあり、いつも以上にお腹いっぱい食べました。
③に続く…
夕方には温泉へ。大きな浴槽に最初は戸惑う子もいましたが、最終的には「まだ入っていたい!」(笑)みんなで入るお風呂は楽しいね!
そして夕食。ビュッフェ形式でサラダやカレーなどを自分が食べたい分だけ盛りつけ。自分たちで育てたり作ったりした事もあり、いつも以上にお腹いっぱい食べました。
③に続く…