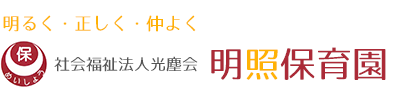カテゴリー
優しい言葉と甘やかし
1月の徳目は「和顔愛語(わげんあいご)」「柔らかい顔で、優しい言葉を」です。「甘えさせる」と「甘やかす」は似て非なるものです。何か頑張っている中でホッと一息甘えられる時間を作る事は大切ですが、本人が出来ること、出来るよう少しずつ練習すべきことを常に代わってあげることや、「子どものすることだから」と自分勝手な行動に制御をかけないままにするのは甘やかしに繋がります。園では「褒める」を意識していますが、何でも褒めているわけではありません。少しでも成長した部分、周囲に惑わされず自主的に行動できた部分など視点を持って声かけしています。また、望ましくない行動には「ダメでしょ」と声をかけて終わるのではなく、どこをどのように修正すべきか一緒に取り組み、少しでも望ましい方向に進むまで伴走するよう努めています。「三つ子の魂百まで」この時期だからこそ、向き合っていきたいものです。
本来全て自分でまとめるべきでしたが、一部AIに代わってもらったこと、お詫び申し上げますm(_ _)m(2026.1)
Losing isn`t an option!
ドジャース山本由伸投手がワールドシリーズのMVPに選ばれました。日本人としては、松井秀喜選手以来2人目という快挙です。今回、選ばれた理由はやはりなんといっても7試合中3試合に登板し、全て勝ち投手となっており、1試合は最後まで投げきっている点です。しかも、現代野球では先発ピッチャーとして登板した場合、4~5試合ほど空けてから次の登板日にすることが一般的ですが、7戦目は中0日、つまり先発登板した次の日に投げるという前代未聞の活躍でした。上記コメントは、完投後中1日の第3戦、延長18回までもつれたことで救援準備をした時のものです。当然のことながら、しっかりと目標を立てた上で地道な努力を重ねてきたからこそ成し得たことなのだと改めて感じました。
12月の徳目は「忍辱持久(にんにくじきゅう)」、「根気強く取り組もう」です。根気強く取り組むためには明確な目標を定め見通しをもつ事が大切です。子どもたちが明確な目標をもつことは難しいかもしれませんが、見通しを持たせ、コツコツ取り組む習慣が身に付くよう関わっていきたいものです。
タイトルは、山本投手の「負けるわけにいかない」という発言を通訳の園田芳大さんが「負けるという選択肢はない」と意訳し話題になった言葉です。園田さんは、私の大学時代からの友人の従兄弟です。まるで知り合いのように紹介しましたが、つまりお会いしたこともない他人です…。(2025.12)
タイパ≠時短
11月の徳目は「精進努力(しょうじんどりょく)」、「最後までやり遂げよう」です。見通しを持たずむやみに時間を掛ける「時間の無駄遣い」は見直す必要があります。しかし、じっくり腰を据えて何かを見聞きする機会が減ることは、辛抱強く取り組んで最後までやり遂げる力を失わせ、目先の利益だけを得る習慣が身に付いてしまうように感じます。「タイパ」とは日本語で「時間対効果」のことで、「タイパが良い」とは「時間が短ければ良い」というわけではなく、「効果的に時間をかけて、より良い結果を得る」という意味が含まれています。子どもの成長に当てはめて考えてみると、子どもはある日突然成長するわけではありません。良い習慣も改善すべき習慣も日々の積み重ねです。腰を据えて物事に向き合える時間を少しずつ増やすことが、子どもたちの良い成長を促していくのだと思います。
結論がすぐに分からないこの文章をここまで読んで下さった方、辛抱強いですね!…腰を据えて読んで頂きありがとうございますm(_ _)m(2025.11)
好敵手
さて、10月の徳目は「同時協力(どうじきょうりょく)」、「お互いに助け合おう」です。助け合うためには同じ目標を共有していることが大切です。そしてそれはライバルであっても、目指すものが一致していればその競い合いが互いを高め合い、結果的に助け合いへ繋がっていくと思います。運動会を通し、「自分の力を出し切る」という目標を共有した子どもたち。次はお遊戯会に向けて協力し合えるよう、10月を過ごしていきます。
「NHKを観ている」と書いたら少し知的に見えるかなと、その魂胆がすでに知的ではない私の文章に今月もお付き合いいただきありがとうございます(^_^;)(2025.10)
心の豊かさ
今月の徳目は「報恩感謝」「あらゆることを有り難く感じよう」です。鬼が、とあるCMで「分けると『嬉しい』が増える」と学んでいるように、丸儲けしたものを独り占めするのではなく、「有り難いことだからこそみんなと共有する」ことが大切です。「欲張らず、ちょっとしたことにも感謝して、みんなと分け合う」心の豊かさをもつことこそが、個を大事にすることに繋がるのではないでしょうか。
先日、「小さく」なった職場のTシャツを着て、みたままつりに参加しましたが、昨年よりお腹周りが「豊か」になっていたことを職員にやんわり教えてもらいました。このため込んだものを何とかして分け合いたいです…(2025.9)
弁当に込める想い
さて、8月の徳目は「自利利他(じりりた)」「自分を高め人に尽くそう」です。料理スキルの向上した子どもたちが作った弁当を見ると、どれも様々な食材を使って鮮やかに彩られています。そして、好きな物、食べたい物をただ入れるのではなく、おいしそうに見える工夫や、栄養を考えて作っていることが見て取れます。弁当を作ってあげる相手の「食べている様子を思い描き」「これからの健康を願う」といった、「相手を想うこと」「未来を想うこと」が体現されているように感じました。今の世の中の「個を大切に」「自由に生きる」は「『今の』自分『さえ』良ければ良い」という思考に陥りやすい危うさを感じます。周りに生かされている私たち。周りのことなど関係なく今の自分に都合の良いことを主張するのではなく、「誰かのために作る弁当」のように、「周りを想い、先を考える」そんな姿勢をこれからも育ててていきたいものです。(2025.8)
手を…
さて、7月の徳目は「布施奉仕(ふせほうし)」「誰にでも親切にしよう」です。「ほら、早く支度しなさい」「急がないと間に合わないよ」と言いながら手を貸して、いつの間にか大人が代わりに準備していたり、食べさせてあげたり、物を持ってあげたりという経験はないでしょうか。大人が動いた方が早いため、子どもに促しているつもりでも、忙しいと知らず知らずのうちに全部やってあげていたなんてこともあると思います。子どもからすると「早くしなさい」と言われてもやってもらえ、自分でやる機会も必要もなく、それでもやるべき事が完了するといった間違った成功体験を積むことになります。お仕事の時は難しいかもしれませんが、例えば、準備や食事の後に子どもの楽しみが待っている時こそ、自分でやれることを増やせるチャンスです。子どもたちの自立への促し方を日々模索していきたいものです。
「俺たちの仕事は、人や会社の成長を願い、その手助けをすることだ。証券も、いや、どんな仕事も目指すところは同じはずだ。【半沢直樹】」(2025.7)
曖昧の大切さ
6月の徳目は「生命尊重(せいめいそんちょう)」「命を大切にしよう」です。人は誰しも良い面、悪い面、両面を持っており、善か悪と単純に二分できるものではありません。自分に都合のよい情報だけを集めてしまうと、正しい、間違っているの二択だけで判断してしまい、他者への誹謗中傷や罰を与えようと攻撃することで快感を得たり、自分で作り上げた怒りに振り回されて苦しんだりします。しかし、柔軟に受け止めることができれば他者にも寛容になれます。ネガティブ・ケイパビリティは自身を大切にするだけでなく、他者を受け入れる力にもなるということです。 「命を大切にする」とは他人も自分自身も大事にすることです。柔軟に考える習慣を身につけ自分や他者を受容する事が、命を大切にする事に繋がっていくと思います。
「ネガティブ・ケイパビリティ」前回のコラムでアレに興味持って下さった方は、何からの思いつきか分かるかもしれません(笑)(2025.6)
保育園のにじゅうろくにん
「団地のふたり」というドラマをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。小説がドラマ化された作品で、生まれ育った団地に舞い戻ってきた幼なじみの女性2人の友情物語を中心に、団地に住む様々な人々とのご近所付き合いを描いた内容です。ここの団地の住人は皆とても個性的で、考え方も多様。それでも大きな仲違いをすることなく、ほのぼのと時間が流れていきます。それは、それぞれ好きなことをしつつも「周りのために」という想いがみんなの根底にあるからなのではと感じます。このドラマは2024年10月のギャラクシー賞を受賞したほど反響がありました。また近年、団地に興味を持つ方が増え団地が再評価されているという話も聞きます。住人同士の会話が生まれるような仕掛けにより、入居者を増やしている団地もあるそうで、改めて人同士生身の関わりが求められ、その重要性が見直されているように感じます。
5月の徳目は「持戒和合(じかいわごう)」「決まりを守り、集団生活を楽しもう」です。自由とはルールの上に成り立つものであり、ルールがないのはただの身勝手、無法地帯です。それでは、どんなルールが必要なのでしょうか。それは、「他者のことを思いやる」という事だと思います。明照保育園の3つのお約束の1つ「仲良く」に繋がります。自分の好きなように過ごすためには、他者と共に生きていることを忘れてはいけません。「自主性」「子どもの好きにさせる」非常に聞き心地の良い言葉ですが、もう一度その意味を考え、子どもたちが本当の「自由」を学ぶために、我慢する機会を設け自身を律する練習をしていきたいものです。
団地ドラマと言えば、現在放送中の新たな団地ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」ご興味ある方は是非ご覧下さい♪テレビ番組最後に行われる、俳優さんの番宣みたいになってしまいました…(2025.5)
インプット・アウトプット
さて、4月の徳目(より良く生きるための基本となるもの)は「合掌(がつしよう)聞法(もんぽう)」「敬う心をもって人の話を聞こう」という意味です。何かを考えたり判断したりするには、まず情報を仕入れる必要があります。何かを発信するときも、まず自分自身に知識や技術、経験の蓄えがないと伝えることはできません。つまり何をするにもまずは「聞く」姿勢、吸収しようとする態度が大切です。インプットすることで、はじめてアウトプットができます。子どもたちの吸収する力は、正しく発揮できる環境がないと間違ったことを吸収してしまったり、衰えてしまったりします。だからこそ、周りの大人が手間暇をかけて育てていかなくてはなりません。保育目標の「正しく」は「おうちの人や先生のお話をきちんと聞くこと」と子どもたちに伝えています。ご家庭と力を合わせて保育していければと思います。
今年度もよろしくお願いします。(2025.4)
コペルニクス的転回
さて、3月の徳目は「智慧希望(ちえきぼう)」、「希望をもち、楽しく暮らそう」です。智慧とは、「気づき」と言い換えることができます。1つの物事でも様々な視点から見ることで違う考え方ができることに「気づく」と視野が広がります。視野が広がると偏った見方から開放され、思い通りにいかないことがあっても感情に振り回されることなく、落ち着いて楽しく暮らせるようになります。物事の見方を根本的に変えるのは難しいことですが、普段の何気ない当たり前を「当たり前だと思う理由は何だろう」と1度立ち止まって考える事はとても大事なことなのだと思います。
番組を観た次の日、どんな言葉が話題になったか立ち止まって考えてみても半分以上思い出せず、やっぱり賢くなった「気分」でしかないと考えさせられます…。(2025.3)
上手くいかないときこそ
2月の徳目は「禅定静寂(ぜんじょうせいじゃく)」、「よく考え、落ち着いた暮らしをしよう」です。イス取りゲームは、最後まで座れるのは1人だけで、それ以外は「座れない」という経験をします。運の要素もあるため、前回最後まで座れた子が次も残り続けられるとも限りません。子どもたちからすると、思った通りにいかない可能性が非常に高いゲームです。でもそれは、普段の生活でもよく起こることだと思います。人は生きている上で全てが思い通りにいくことはありません。だからこそ、上手くいかなかったときの行動がとても大切で、次に繋がるかどうかはそこにかかっています。悔しさを感じることは大切ですが、それを怒りや悲しみとして爆発させても何の解決にもならないどころか、事態を悪化させたり他者を傷つけたりする可能性すらあります。思い通りにいかないときは1度立ち止まって落ちつき、よく考えて行動することが大切です。成功体験を多く経験させることで自己肯定感を高めつつ、そんな経験も積み重ねていければと思っています。(2025.2)
社会貢献
1月の徳目は「和顔愛語(わげんあいご)」「柔らかい顔で、優しい言葉を」です。自分だけが楽しい思いをするのではなく、周りも笑顔にすることが求められます。そのためには「自分さえ良ければ良い」という独りよがりや「周りが○○してるから自分も」と、他者に判断を依存する姿勢から離れ、何が皆にとって良いことなのかを自ら考えることが大切です。自分の欲求とどう折り合いをつけるのか、どのように感情をコントロールするのかを身に付けることは簡単ではありません。今の時期から少しずつ譲ったり我慢したりと気持ちを切り替える経験を積み重ねていくことが「社会貢献」という行動の第一歩になるのだと思います。(2025.1)
自信偈
お釈迦様がどうしたらみんなが幸せになれるのか考え悟ったことは、これまでの宗教の考え方とは異なるものでした。そのため理解してもらうのは非常に難しく、お釈迦様自身もみんなに伝えるかどうか悩んだほどでした。実際に、かつて一緒に修行した仲間に悟ったことをそのまま伝えても理解してもらえず、たとえ話などを織り交ぜて伝えることでようやく理解してもらえたそうです。
12月の徳目は「忍辱持久(にんにくじきゅう)」、「根気強く取り組もう」です。お釈迦様が根気強く取り組み、核はそのままに、その時代時代に合わせて伝え方を試行錯誤したことにより数千年経った今でも仏教の考え方が生き続けています。だからこそお祝いする成道会があります。
子どもたちがこれまで新たに学んできたこと、身につけてきたものを総動員してお遊戯という形に落とし込み、これまでの頑張りをお家の人に見てもらおうと一生懸命取り組んできました。そんな子どもたちの成長した姿をどうぞお楽しみください。(2024.12)
自尊心
11月の徳目は「精進努力(しょうじんどりょく)」、「最後までやり遂げよう」です。最近よく「ありのままで良い」というフレーズを耳にしますが、それは、「今の自分で十分」という現状に満足することを意味するものではなく、自分の短所も含めた「ありのまま」を受け止め、自分は更に成長できると信じながら先を目指すことなのではと感じます。短所を「ダメ」ではなく「伸びしろ」と捉え精進していくことが大事です。そのような意欲的な姿勢を育てるためには、「自分で出来た」という達成感を味わう機会を作りつつ自分の行動に責任を持たせる事が重要です。どうしても大人に余裕がないと「早くしなさい」や「○○させないからね」と声をかけてしまったり、結局やってあげてしまったりと、周囲からの働きかけがないと行動しない、またはやってもらうのが当たり前になってしまいます。子どもは現在何ができるのか、どんなサポートをどのくらいしたらできるのかを見極め、くつを片付ける、通園カバンを背負う、上着を着るなどといった普段の何気ない場面での関わり方、ご飯を食べる時や寝る時などその活動が落ち着いてできる環境の作り方を模索し積み重ねていくことが、自尊心を育てる土台になるのだと思います。(2024.11)
切磋琢磨
さて、10月の徳目は「同時協力(どうじきょうりょく)」、「お互いに助け合おう」ということです。「協力」という言葉からは、「同じチームや組織で力を合わせる」というイメージが先行するかもしれません。しかし、今回の大谷選手の記録を巡る周囲の言葉を聞くと、真剣勝負で互いに高め合うような、例え同じチームではなくとも同じ志を持ちしのぎを削ることもまた、広い視点から見ると協力することに繋がるのだなと感じました。もちろんそれには、大谷選手の謙虚でひたむきな姿があるからこそ周りも呼応し、高め合っていけるのだと思います。周囲を想い共に成長しようとする姿を育てていきたいものです。(2024.10)
めったにない
先日のみたままつりはいかがだったでしょうか。仏教行事を絡めた夕涼み会のため、出店や盆踊りだけではなく、ご先祖様に想いを巡らすおつとめも行います。私たちはご先祖様が繋げてきてくれた「命」のお陰で生かされています。お盆は過ぎてしまいましたが、今度はお彼岸がやってきます。お彼岸の中日は、太陽が真西に沈む秋分の日と同日です。亡くなった方が向かう世界を「彼(か)の岸」と言い「極楽浄土」という場所があります。「西方浄土」とも呼ばれ、西の方角にあるとされているため、正確な西を知ることの出来る秋分の日がお彼岸の中日でもあります。どうぞ、お墓参りなどをして改めて命の繋がりについてご家庭でも考えるお彼岸にして頂ければと思います。
今月の徳目は「報恩感謝」「あらゆることを有り難く感じよう」です。繋がってきた命を今度はどのように活かすかが大切です。来月には運動会がやってきます。仲間に感謝し協力することも、ライバルがいることに感謝し切磋琢磨して競争することも命を活かす方法の一つです。ステキな運動会になるよう職員一同頑張ります。
クイズの正解です。10代前のご先祖様は1,024人です。ちなみに、20代さかのぼると1,048,576人のご先祖様たちがいて、両親から20代前までの人数を全て足していくと、現在の青森県の人口約120万人を超える2,097,150人になります。改めて考えるとすごい数で、そのうち1人でも欠けていたら、私たちの命はありません。ご先祖様たちとの“奇跡的”な連なりで、私たちの命は繋がっているんですね。(2024.9)
仲良く
さて、8月の徳目は「自利利他(じりりた)」「自分を高め人に尽くそう」です。保育園のお約束「明るく・正しく・仲良く」の「仲良く」について、子どもたちには「お友達に『ありがとう』と言えたり、お友達から『ありがとう』って言ってもらえることをしよう」と話しています。「僕はこれをしたくないから」「私はこっちをしたいから」とみんながそれぞれ好きなことをするだけでは、「チャレンジする」といった積極性が育たないだけでなく、そもそも集団行動の意味がありません。みんなで同じ事を共有する機会があるからこそ、他者を思いやる力が身に付くのだと思います。だからこそ、まずは目の前のことに取り組む習慣を身につける事が大事なのではないでしょうか。行動に移せない原因には、慣れていなかったり、見通しがもてなかったりと経験不足によることも多くあります。乗り気ではないからと本人の要求をそのまま受け止めるだけではなく、取り組める環境を整え促すこともまた大事なことであり、その積み重ねが積極性や思いやりの土台となっていくのだと思います。
目の前の仕事が文字通り机の上に山積みになってることもありますが、コツコツ取り組まなければと思いを新たにできました…(2024.8)
親切と深切
さて、7月の徳目は「布施奉仕(ふせほうし)」「誰にでも親切にしよう」です。「布施」は「(品物などを)あげる」「奉仕」は「やってあげる」といったイメージがあるかもしれませんが、相手が成長できるのか、前向きになれるのかが非常に大事なポイントであると感じます。自分自身の子育てを振り返ると、何かをしてあげることは簡単で手っ取り早いため、とっさにやってあげていることがあったなと感じます。皆さんは如何でしょうか。
子どもの成長や前向きな姿勢に繋がるのかをその都度考えてやってあげるかどうか、やってあげるとしてもどこまでやってあげるのか判断する、もう一度心に留めておきたいものです。(2024.7)
想いを繋ぐ
現在、アニメ鬼滅の刃第5弾柱稽古編が放映されています。鬼滅の刃は残虐な描写もあって、子どもに見せることは賛否両論あり、私も子どもへの影響は慎重に考えなければならないと考えています。しかし、ストーリーの完成度はもちろんのこと、物語の様々な部分に仏教の考え方がちりばめられており、私自身非常に興味深く見ています。先述の台詞は、主人公の炭治郎が過去の出来事により立ち直れずにいる水柱、冨岡義勇の背中を押した言葉です。「想いを繋ぐ」は鬼滅の刃の大きなテーマの1つだと思いますが、このことで、義勇は自分の命を活かすことができ、鬼殺隊が本当の意味で一枚岩になるための重要な場面となりました。
さて、6月の徳目は「生命尊重(せいめいそんちょう)」「命を大切にしよう」です。どんな命も突然生まれるのではなく過去から脈々と繋がっており、周りに支えられ命が生かされています。だからこそこれまでを大切にし、周りに感謝し、次に繋げることを考えていくことが回り回って命を大切にすることになると思います。「個」を大切にすることは必要ですが「自分『だけ』」ではなく「自分『も』」という視点が重要です。自分のやりたいことが自然と周りを想うことに繋がっているような子どもたちが育っていく環境をこれからも模索していきます。
鬼滅の刃と仏教を絡めて論じているお坊さんは実は結構います。その中でも稲田ズイキというお坊さんのお話は、現代と仏教を考える際に私が一番の拠り所にさせて頂いている方です。ご興味があれば是非検索してみてください。(2024.6)